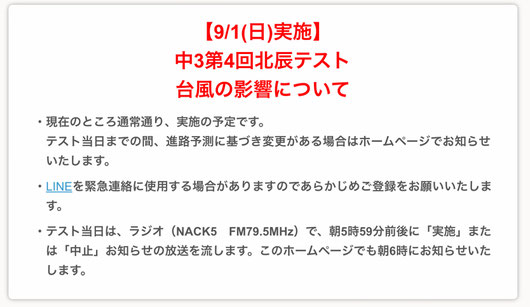新学期

節目として、何かを始めるには良い時期だ。それがぜひ勉強であってくれると嬉しいのだが。
勉強の最初は"自分探し"となる。まずは自分がどこからスタートする必要があるのか、それを自分で見つけていくことになる。今までに習ってきたことを振り返り、できていないところを見つける。きっと楽ではない。なぜなら自分の弱いところと向き合うことになるからだ。しかしここで逃げてはいけない、ここで逃げてしまったから自分は今の学力、成績なのだ。それと向き合い、克服しようと1つずつ取り組むことによってそれまでの自分は過去のものになり、新しい自分になっていく。成績は誰かが上げてくれるものじゃない、学力は誰かが伸ばしてくれるものじゃない。全て"自分事"として取り組める人だけが殻を破っていく。
差し入れをいただきました!

ポストの横にあるので欲しい人はどうぞ。
新入生募集

小4〜高3
弊塾では自立学習というスタイルで指導しております。
ご興味がある方はメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
指導合格実績(一部)
大学
千葉・埼玉・宇都宮・山形・埼玉県立・早稲田・慶應・東京理科・青山学院・立教・明治・法政・学習院・芝浦工業
高校
浦和・浦和第一女子・大宮・春日部・越谷北・蕨・不動岡・越ヶ谷・川口北・早稲田・早稲田本庄・立教新座・栄東・中大杉並・大宮開成・淑徳与野・駒込・正智深谷・獨協埼玉・昌平・春日部共栄・國學院栃木
合格発表

先ほど最後の生徒が報告にやってきて、弊塾の塾生たちからも全て報告を受けた。残念ながら全員合格とはならなかったが、今は全員の奮闘を労いたい。
もちろん自分の関わった塾生には全員笑顔になってもらいたかったが、受験は公平ではなく平等なもの。こういう結果も受け止めなくてはならない。
しかし、今年は本当に予想を超えた合格者が多数出る結果となった。
申し訳ないが正直もっと堪える結果を覚悟していたので、良い意味で少し肩透かしをくらった。おそらく、自分自身の予想が「私が指導した効果」を加味したものだからだろう。私が"手取り足取り丁寧に"指導していたらきっともっと不合格者が出ていた。この結果は生徒本人の力によるものだ。そう考えると自分の"指導方針"をより信じられる結果になったが、自分の進路指導の腕はまだまだだということでもある。そしてそれを伸ばしていくには、生徒の「潜在能力」をもっと"信じる"必要が出てくる。自分自身の技術ではなく、自分ではどうしようもない部分を信じるのは怖い。"信じる"と言う都合のいい言葉で、相手に責任を押し付けることにもなりかねない怖さがある。しかしそろそろ次のステージに上がるには、勇気を出してそこを模索していく必要も出てきたのだろう。
そして、今回受験を戦った塾生の皆さんへ
不合格だった子は残念です。先生も悔しい。
もしかしたら今、自分を全否定されたような衝撃を感じているかもしれません。
でも、ここまで頑張ってきたことは私がしっかり見届けました。
それは決して無駄なことじゃない。間違いなく自分の成長につながっているんだ。
だから今は泣いていてもいいから、いつかはまた立ち上がって前を向いてください。
これで終わりじゃない、まだ"次"がある。
今日の悔しさを忘れないで。それは絶対に自分のエネルギーになるから。
またいつか、自分の通っている学校の制服を誇らしく着ている姿を見せてくれたら嬉しいです。
合格できた子はおめでとうございます。
ここまで頑張ってきた結果が実ったことを喜ばしく思います。
その努力は、毎日積み重ねた学習記録シートの厚みが証明してくれてますね。
でもここからが本当の勝負です。
まず絶対に言えるのが、高校には「自分よりできる人」がいるということです。
学校の中で負けているようでは、"次"を戦うことなどできません。気を引き締めて。
ここで勉強を辞めてしまうような人にだけはならないでいてください、先生からのお願いです。
そして、気づいていてくれると嬉しいのですが、
君たちの勉強は、「君たちだけのもの」ではありません。
ここまでやってこられたのは誰のおかげでしょうか。
お腹がすくとすぐにフラフラと集中を乱す君たちでも
毎日飢えず、凍えず、そして更なる成長の機会を与えてもらいました。
そのことをよく考えて。今すぐ横を見て隣の人に一言、
「応援してくれてありがとうね」って言ってもいいんだよ。
その気持ちを忘れなければ、これからの君たちの活躍は約束されたようなものです。
そんな期待を込めてエールとさせてもらいます。
受験生の皆さん、お疲れ様でした。
元塾生の訪問

今日は元塾生が訪問してきた。聞くと、わざわざ大学合格の報告に来てくれたそうだ。
そうか、もうそんなに経ったのか、と思う。毎年受験生を送り出してはいるが、彼が卒業したのが3年前。その頃とは見違えるほどに背の伸びた彼の姿からも流れた時間を感じる。
ここに塾を立ち上げてもう10年、多くの生徒が訪、時を過ごし、巣立っていった。今年の受験生ももういない。この時期はいつもこうだ、教室がやけに広く感じる。私は姿は見違えたが話し方は3年前の癖を残している彼の言葉を聞きながらそんなことを思った。
我々は子供の学力を伸ばし、そして送りだすのが役目。最後に瞼の裏に焼き付くはその後ろ姿だ。だからこそこうして目を見て「合格おめでとう」と言えたことに感謝したい。頑張れ、これからも応援してる。
差し入れをいただきました!

卒業生から差し入れをいただきました!ありがとうございます。
ポスト横にあるので欲しい人はどうぞ。
公立高校入試

本日は埼玉県立高校入試が実施された。
弊塾からも受験生たちが試験に臨んだ。実力が発揮されていることを願う。
昨日が入試前最終日だったので、まとめたアドバイスとちょっとしたお守りを渡した。もちろん教え子には全員望む進路に進んでもらいたいとは思っているが、受験に与えられた時間は平等で、それは受験生になる前から始まっていた。その中で積み上げたものが受験結果となるので”横入り”はできない。傍目に大逆転合格をしたように見える子は横入りではなく後ろから一人ひとり抜かしていった結果だと思っている。そういう意味でも受験は平等だ。
そう思うことで感傷を排除しようと試みる。本気の勝負へ送り出すというのは毎年行っていても慣れるものではない。
私立高校入試

試験を終えて教室に来た生徒に感想を問うと、
「北辰より緊張しました。」と。
確かに模試は本番に向けた"場慣れ"の意味も過分にあるが
それでもやはり本番に勝る緊張感はないだろうと思う。
そういう意味でも私立高校入試は公立高校が第一志望であっても受けておいた方がいいと思う。
少子化により"全入"がスタンダードになりつつある地域もあると聞いた。
その地域の生徒はいわゆる"滑り止め"を受けないのだそうだ。第一志望全入だからね。
今までの講師生活で、滑り止めを受けずに第一志望を受けた子を数人知っているが、
これまでこの地域だとそれで上手く行くことはあまりなかった。
この地域の高校はもうしばらくは志願倍率は1倍を越え続ける。
そんな黄昏の時代にあって、学生の時期にヒリヒリする体験をできることはある意味貴重なのではないか。
まもなく受験でヒリヒリできるのは、一部の限られた生徒だけのものになる。
【塾生のみなさんへ】差し入れをいただきました!

生徒から差し入れをいただきました!ありがとうございます。
ポストの横にあるので欲しい人はどうぞ。
2025年

新年明けましておめでとうございます。
今年も皆様のご多幸とご健康をお祈り申し上げます。
さて今日から授業が再開した。
まずは冬期講習から行い、受験生たちの状況をチェックした。
年があけてしまえば入試まではあっという間だ。
最後ラストスパート頑張ってもらいたい。
受験対策冬期講習

昨日から中3の冬期講習が始まっている。
冬期講習は短い日程の中で効果を狙っていかなくてはならない。
復習の内容を1から解説して、余った時間でちょっとだけ問題演習して、みんなで丸つけして間違えが多かったところを再び解説・・・なんてやっていても生徒の学力は伸びない。
以前、年が明けてから塾の見学に来られた受験生親子がいた。
なんでも今通っている塾の冬期講習では
「"問題を解いて解説するだけ"で全く意味がなかった」とのことだった。
それは弊塾が採っている冬期講習の指導方法と同じだ。
おそらく親御さんとしては学校みたいに全ての内容を授業して欲しかったのだろう。だが、おそらくその塾では夏期講習にそういった指導をして、ある程度仕上がった生徒たちを想定した冬期講習を行なっていたのではないだろうか。その生徒はその流れに乗れていなかったのかもしれない。そのズレによる"不満"。結局入塾に至ることはなかったが、少し気の毒に思った。
弊塾の冬期講習ではここで半年過ごしている子を相手にする。問題を解くときは何も言わなくても解き終わったら「はい」と返事して私が測っているタイムを確認するし、口頭で話したこともメモしている。
塾とは、勉強とはカンフル剤のようなものなど無い。しかし冬期講習ではそれに少しでも近いものを提供するためにこの半年間はあったのだ。
【塾生のみなさんへ】差し入れをいただきました!

保護者の方より差し入れをいただきました!ありがとうございます、
ポストの横にあるので、ほしい人はどうぞ。
大学合格!

生徒が大学に合格した。
先程その報告に来てくれた。おめでとう!
自学の力を伸ばすことを求めて指導を続けていると、
年々「自分が何かをやった」、もっと言うと「私が生徒を伸ばした」「私が生徒を志望校に合格させた」という気持ちは希薄になっていく。
生徒はあくまで自分で頑張り、自分で道を切り拓いただけだ。私はその伴走をしたに過ぎない。
だから自分の達成感が満たされるわけでは無い。感じるのは、「よく頑張ったね」という労いの気持ちと幸せを喜ぶ気持ちだけだ。
達成感は無い、でも昔のエゴイスティックな指導をしていた時よりも素直に人の幸せを喜べている気がする。
【塾生のみなさんへ】差し入れをいただきました!

保護者の方から差し入れをいただきました!
ありがとうございます~。
ポストの横にあるので、ほしい人はどうぞ!
期末テスト直前

今日は埼玉県民の日で近隣の中学校はお休みだそうだ。
だが今日も教室が開くなり受験生たちが自習にやってきた。受験生は期末テストまで残り4日、1・2年生も残り2週間だ。休んでいる暇などない。
学校の英語のワークには長文問題が載っていて、その訳を一緒に確認してほしいと生徒が言ってきたので行った。ワークの長文も学校の定期テストで出されるのでテスト対策だ。最近の学校の英語ワークは難しい。おそらく学校で平均点前後の子ではきちんと日本語訳を取ることはできないだろう。今日確認した文章にも<命令文,and>構文や不定詞、現在完了などの文法もふんだんに盛り込まれていた。指導しないと絶対に「なんとなく読み」に生徒が流れてしまうやつ。それを許していると、取り組むほど英語の力を弱めてしまう。
子供が国語できないのは大人のせいだよ

「せんせートイレ」
「先生はトイレじゃありません」
昔こんなネタがあった。生徒が言葉足らずで起こるやり取り。なんとなくこれ小学生のイメージだったのだけど、今は中学生や高校生でも普通に起こる。全く笑えない。
単語のみによる会話は言語能力の成長を阻害する。学校の定期テストで平均点前後くらいから「文章で話す」ことのできない子が増える。再テストの申し込みをする時も
「先生平行と合同の3番」
とやって来る。先生は平行と合同の3番じゃありません。
こういう生徒は国語の記述問題が解けない。「なぜですか」と問われているのに「~こと」と答えたり、「何ですか」と問われても「~している」と答えたりする。言葉のやり取りができていない。普段単語で会話をしていることの弊害はこういう所に出る。
周りの大人が「察して」会話を成立させていてはダメだ。きちんと何がどうなのか、本人の口で説明させることが国語力アップにつながる。
認めてもらいたいんだから

「家で手伝えることはありますか」
面談で保護者の方に結構聞かれる質問だ。生徒が勉強を頑張り出すと、親としても何かしてあげたいと思われるのだろう。
「お子さんが勉強している時、そばにいてあげてください」
私の回答はだいたいこれ。ちょっと拍子抜けに感じさせてしまうかも知れない。でも子供の勉強には一番効果的な気もする。遊んでしまうことへの抑止力とひとりでやる心細さへの安心感。これに勝るサポートってあるのかしら。「見ているよ」というメッセージ。それ以上はいらないし、それこそが欲しい。
テレビを消して勉強する子の隣で読書なんかしてたりしたらこれ以上のものはないと思っている。親の背を見て子は育つのだから。
半年後に成績に出る

塾の小テストの準備を当日に行っている生徒がいる。
弊塾のルールは小テストの準備は当日「までに」行う。つまり前日までに完成しておいてくださいというもの。だから入塾面談でも自習に来ることをお願いしている。したがって当日来て準備をしているのはルール違反ということになる。
まずなぜこのルールにしているのか。それは学習量の確保が目的だ。勉強は毎日行うべきもの。しかしいきなりそれはできないだろうからまずは授業の日と自習の日、最低でも2、3日は塾に来て勉強してほしいと思っている。じゃないと成績なんか絶対に上がらない。
理由があってたまに当日準備になってしまうくらいならば仕方がない。だがズルズルと当日準備になっていく生徒は面倒くさがってそうなるわけで、他に日に自習になんて来やしない。楽をしようとしているわけだからね。そうすると小テストも合格できなくなるし、そもそも準備が間に合わないということが発生する。そうなった段階で指摘はしている。それで変わってくれればいいんだけどね。
そういう生徒の成績は徐々に下降線をたどる。成績が下がったと気づいたときにはもう取り返しが付かないほどの負債を抱え込んでいる。成績が下がるには理由があり、それは時間をかけて影響を及ぼしているのだ。今週やるべきことを怠っていないか、それをもう一度よく考えてみてもらいたい。
自分の原体験

学生時代に家庭教師のアルバイトで「オール1」の生徒を指導したことがある。
別に学校に行けていないわけじゃないし素行が悪いわけじゃない。普通の男の子。そして普通に学校に通っていてオール1。今ならなぜそんな成績になるのか詳しくご両親から話を聞くが、その時は「そんなものか」くらいに思っていた。
指導が始まると確かに問題は全く解けない。中3の段階で数学の力は小学校4年生くらいだった。でも受け答えはちゃんとしてる。挨拶もできる。これならいいける、と思った。保護者の方からの要望は「なんとか高校に入れて欲しい」だったし、私はまだ自分の力を過信していた。
指導が始まって少しして、生徒が暗記テストでカンニングをした。成績の理由はこれか、と思った。学校でも常習なのだろう、割とあっさりやった。学校の先生に見つかっていたかどうかは知らない。しかしこの逃げ癖を直さない限り成績は上がらないと思った。私は生徒宅で即座にブチ切れた。お母さんが心配して部屋に入ってくるほどだったが関係ない。ここで変わらなければ学力を伸ばすことなんて無理だ。私はクビになる覚悟でヤンキーよろしく巻き舌で怒鳴り散らした。生徒は辞めなかった。根性があるなと感じた。そこから私も本気になった。時間の許す限り生徒宅で指導を続けた。数学はなんとか中学生の計算、英語は簡単な文法と英文読解くらいまではできるようになっていった。
ある日指導が終わりお母さんと話をしていると、
「最近ウチの子に口喧嘩で負ける」
と言われた。なんでも「口調が先生(私)に似てきた」とのこと。私の思考回路を自分にコピーしてくれているようで嬉しかった。勉強は「真似る」こと。お子さんを生意気にさせてしまった申し訳なさと学びを実践してくれている喜びを感じた。
受験期、都立高校第一志望で私立高校の併願校を1校立てていたが、直前になりもう1校私立校受験を増やすことになった。聞くと「学校の先生に『受けるよう』言われた」と。その学校は偏差値こそ37だったが、保育科のある専門コースの学校だった。私の不安は的中し、その学校には不合格になった。聞くと面接があったのに、中学校では何も対策がなかったということだった。明らかに学校のリサーチ不足でその子に土が付いた。私は憤ったが、その後私が勧めた私立高校は合格だったので生徒のメンタルはなんとか保つことができた。
そして都立高校受験。受験するのは偏差値44の高校。通知表は明らかに足りていない。学校の先生にも考え直すよう言われていた。が、もう揺るがなかった。受験し、無事合格。
最終日、生徒のご両親が私を食事に誘ってくれた。
そこで私が
「学校の先生に『ざまあみろ』って言った?」
と聞くと、その生徒は
「そんなこと言いませんよ」
と返してきた。どうやら全く私には影響されていなかったようだ。本当に良かった。
何を見るか

今日は3連休の最終日か。生徒が早くから教室に来たことで気が付いた。
昨日は用があってある大学の学園祭を少し覗いてきた。学祭は学生のためのものだと思うので私のような部外者が楽しめるものではないが少し気付きもあった。
その大学に誰が興味を持っているか。それが学祭に行くとちょっと分かる気がする。受験生が興味を持っている場合は受験生本人が、親が興味を持っている場合は親が子供と一緒に訪れるのではないだろうか。他にも地域に根付いた大学ならば地元の人が多くいたり。その大学の本当の評価ってこんなところに出るのかも知れない。
受験生が志望校選びで高校や大学の行事に参加しているのを、「普段の様子が分からないんじゃあんまり意味ないんじゃないかなぁ」なんて思っていたのだが、こういう視点は役立つかも知れない。同じように来ている他の生徒の雰囲気とかね。
解説はあるんだろうね?

ちょっと憤っている。
生徒が持ってきた学校で出された数学のプリント、難関私立高校の入試問題が載っていた。明日北辰テストだぞ、それ今やる意味あんの?
例えば今指導している分野の問題だったりすればまだ分かるのだが、普通に中受でやる問題を高校受験向けにアレンジしたような、この辺りの私立高校では出そうもない問題だった。意図が分からん。おそらく学校でも数人しか解けないだろう。それを方程式もまだ覚束ないような子もいる公立中学校で生徒にやらせる意図は。
「こんな難しい問題だってあるんだぞ、すげーだろー」だったらめっちゃむかつく。そんなマウントに生徒の貴重な時間を使わせんな。質問に来ちゃったから解説したけどまるで無益な時間だった。下に正解だけ載せたプリントの作りになってたけど、ちゃんと方程式も覚束ない子にも分かるように解説はしてくれるんだろうね。無責任なことはしないでくれよ、って思う。
【塾生のみなさんへ】差し入れをいただきました!

保護者の方より差し入れをいただきました。ありがとうございます。
ポストの横にあるので、ほしい人はどうぞ!
あと3週間で内申点が決まる

中3の2学期期末テストの範囲表がもう出ている学校もある。なのでテスト範囲表を持って来てくれた子に合わせて教室内のカウントダウンも始めている。期末テストまで残り20日、3週間を切った。あと3週間で受験に持って行く成績が決まってしまう。
定期テストで成績が上がる子とそうでない子の分かれ目はこの時期からテスト勉強にきちんと身が入るかどうかだと思う。生徒の学力段階には差があるので一般化するのはちょっと大雑把な話かも知れないけれど、塾の生徒の勉強の様子を見ているとだいたいそういう傾向にある。今までの成績に変化が見られるのがここから準備を始めた子。多くの学校でテスト範囲表が配られるのが2週間前。それまで何もしないでいると同じような結果に終わる。
もちろんこの時期の受験生の場合は毎日勉強しているはずなのでこの限りではない。ただし受験生であっても、毎日勉強をしている子が更にブーストをかけるのがこの時期だ。そうすれば競争が激しくなっている今でもまだ成績は上げられる。次の日曜には北辰テストもあるが、どちらも手を抜かず全力投球で頑張っていこう。
効率ばっかりの子は

「効率」ばかり求めると成績の伸びは鈍化すると思っている。無駄だと思うことにも養分はあるからだ。
学校のテストなどで満点やそれに近い点数を取る子は、総じて雑学の量が豊かだ。全く関係無いところで身に付けた知識などが問題解決のヒントになることも多い。少し話がブレてしまうかも知れないが「よくそんなこと知ってるね!」とある子に言ったら「ゲームに出てくるアイテム名で身に付いた」と言っていた。言われてみれば私もテレビやしょーもない本を読んでいたおかげで知った漢字や表現などもある。回り道で拾ったガラクタにも見えるものこそが本道のライトアップにつながるのだ。
そんな考えだもので「学校で習ったものだけ」とか「テスト範囲のページだけ」みたいな勉強をしようとする子を見ると大変残念に感じる。特に咎めることはないが、それではテストで満点は絶対に取れないよ、と心の中で思っている。もちろんその子の学力段階で、あまり手を広げすぎないほうがいい時期というのはある。そういう時は私が指導の中で範囲を絞っている。
だが自分の裁量に任された勉強をするときに「ここだけ」と自ら限定してしまう生徒は、どこかで知的好奇心の弱さを感じてしまうし、そんな勉強していても「つまらないだろうな」と思ってしまう。これがたまらなく残念だ。この子にとって、本当の学びは勉強の中には無いのだろうな、と。ただの手段としての勉強。そんな無味乾燥なものを毎日摂取していると思うと悲しくなってしまう。
学力的に優秀な学校は知的好奇心旺盛な子が集まっている。自分の好きなことはとことん追求しようとするし、自分の好きなもの以外にも面白さを見出そうとする。自分もそんな子たちに囲まれた学校生活を送りたければ、勉強でもっと遊ぼうとしておいたほうがいい。サプリメントみたいな、手段としての勉強でそんな学校に行ったって、周りの子の肥えた知的好奇心の舌にはついていけない。
いつ自分で歩けるようにさせますか?

ある指導の結果、姿勢が受け身になってしまっている子というのがいる。こういう子の成績が下がってきて塾なとに通う場合、2つの学力を回復させる方法があると考える。
1つは、生徒が本来持つ「自学の力」を呼び起こして自分で学力を回復させ成績を上げる方法。そしてもう1つは、受け身の姿勢のまま塾に成績を上げてもらう方法だ。
前者は弊塾が取っている方法だが、後者の方法について考えてみたい。近隣の公立中学校ではガイダンスを行って、入学前の小学6年生に「毎日『学年+1時間』の自学をするように」と伝えている。中1ならば1日2時間、中2なら3時間、中3なら4時間だ。実際にできている生徒は多くないだろう。弊塾で実際にこれをやっている子は確実に成績が上がる。
だからこの学習時間を塾の指導時間で補うことになるだろう。集団講義だと受け身のままで自学にならないから個別指導でこの時間の指導を依頼することになる。安く見積もっても相場は1時間3000円円くらい、中3で毎日4時間×週6日とすると週24時間、月96時間。ざっと月額28万8千円也。大学受験の場合は自学の時間が2000時間は欲しいところ。高3からやると1日6時間、中3生の1.5倍か。いい商売だ、やろうかな。月43万円くらいなら我が子のために出してくれる親御さんもいるかも知れない。これくらい指導時間をもらえたら結構どんな子でも成績を上げる自信はあるのだが。
まあ、こんなの当然現実的ではない、冗談はおよしなさいということだ。やはり魚を取ってあげていてもどこかで必ず破綻する。だから魚の取り方を教える必要があるんだ。
私の経験上、中学受験を経て中学や高校で成績が下層の子、集団塾(個別指導塾でも)で高校に行き高校でやはり成績が下がってしまった子などはだいたい受け身、「やらされてきた勉強」の姿勢のままだ。そういう生徒が弊塾のスタイルに乗れるまでには結構時間がかかる。ずっと神輿に担がれたままで足腰が完全に弱っちゃってるからね。
だからそこからリハビリしていく必要があるのだけれど、だいたいこういう場合親御さんのほうが我慢しきれない。1年経たないくらいですぐ辞めちゃう。もしかしたらそれまでの成績が、子供が自分で地面を蹴って走っていたものと思われているのかも知れない。ガリガリの我が子の足を直視しないで「もっと速く走れるようにならないんですか?」と言っているようで見ていて心が痛む。
生徒の成績が伸びると、自分の反省が進む

中学生の中間テストの結果が返却されている。まだの生徒は返却されたら見せてください。
新しく入塾した子も含めて、今の所点数は上昇傾向にあるようだ。1学期との比較だと粗点は下がっている生徒もいるが、平均点からの乖離は大きくなっていれば順位は上がっているだろう。
これは別に弊塾の指導がすごいとかそういうのではなく、生徒が勉強する環境に身を置いて出した結果に過ぎない。綺麗事を言うつもりはないが、生徒が元々持っていた力を出しているだけだ。反対に言うと、それまでやっていなかっただけ。または力を上手に出せていなかっただけ。
弊塾ではその力を発揮するための環境作りをしている。力を効果として発揮するための回路がつながっていない状態をつなげるための環境。
自学力向上を目指し、それゆえ放任主義をとってから自分が生徒を伸ばしているという思いが希薄になった。昔講師のアルバイトなんかをしていた時はそんな自意識バリバリだった。「あいつは俺が合格させてやった」みたいなね。しょーもない。そんなこと考えている暇があったら生徒が伸びる方法をもっと考えるべきだった。今はそれを実践している。
テスト直し、本気でやってる?

中学生の2学期中間テストがボチボチ返却されはじめている。中3生から返却された答案を見せてもらっているが、今見ている限り理科は全員が90点オーバーだった。
まあ良い成績の子は早く見せに来る傾向があるものなので、あくまで今の所は、である。とはいえなかなかの好成績なんじゃないか。他の科目でも90点以上の答案が続々と集まっているので、受験生としての底力が発揮されてきている。やはり結果を出すのは日々自習に来て勉強している子たちだ。
さて、定期テストの結果を持ってきた生徒には「テスト直し」をするように伝えている。伝えてはいるのだが、効果的にできる生徒とそうでない生徒がいる。その線引きは「次同じ問題が出たら絶対に正解できるようになる」かどうかだ。
ただ正解を見て「あー分かった分かった」では絶対に次も間違えるし、これではテスト直しの意味が無い。だったら次の範囲の勉強でもしたほうがマシだ。こんなぬるいやり方ではなく、自分が間違えてしまったことを悔いて、次は絶対に間違えないと思えるかどうか。定期テストの直しは徹底的に自分を「打つ」作業だ。それができる子だけが、次のテストで結果を変えていける。
定期テスト直後は塾のスキマ時間

中学生は中間テストが終わったところ。答案・個票が返却されたら塾に持って来てください。
定期テストが終わった直後の授業ではそれまでの復習や少しハイレベルな内容などを行う。テスト勉強をしてきた状態の頭は知識を吸収しやすくなっているし、生徒も定期テストへ注力していたこともあって予習が進んでいないこともある。だからそれを考慮してやる内容を決めている。
昨日は受験生に入試問題の少しハイレベルな英文を読んでもらった。文法の学習が一通り終わっている子は次は長文読解の練習だ。今文構造を読み解く練習を多く積んでおくことは、冬以降の英語の得点力アップにつながる。
難関校の入試問題の英文は公立高校の英文とは少し違う。単語を知っていても文構造が複雑で訳しにくいものが入っている。これは構文解釈の練習にもってこいだ。ホワイトボードに英文をピックアップして文構造を分解しながら訳す練習を行った。学校で習う内容だけでは入試に対応できない科目もある。そこを補って伸ばしていくのが塾の役割のひとつである。
一定のペースで進めるか

本日で中学生の2学期中間テストが終わった。塾生の出来はどうだったろうか。
テストは終わったが生徒の勉強は終わらない。本日も教室を開けるなり受験生が勉強に来て頑張っている。常に一定のペースで勉強が続けられる生徒は伸びる。そういう子はテストの前後で行動が変わるなんてことはない。
昔働いていた塾ではテスト前に授業の「前倒し」というものがよく行われた。テスト当日夜や翌日の授業をテスト日の前に移動させて行うのだ。保護者の方から申し出てくることもあれば、塾の方から提案してしまうこともあった。
それでその効果はというと、まあ全く意味は無かった。結局テスト前って授業をやることよりも生徒本人の勉強のほうが大切だからね。意味があるとすれば、保護者に対する手厚い指導の「ポーズ」が取れるってことくらいか。生徒の勉強時間を奪っておいて何が手厚いなんだかと今では思うが、勉強のことをあまり知らない親御さんには喜ばれた。
今は授業の前倒しはしない。そんなもので上下しちゃうテストの点数って実力なの?って思うからだ。せいぜいテスト直前の授業ではテスト科目の勉強に付き合ってあげるくらい。過去に成績上位だった生徒たちはテスト前日の授業でも休むことなく普通に受けにきている。そしてテスト範囲外のことであってもきちんとやり遂げるし、こちらが何かテストのことで手伝ってあげようとしても「大丈夫です」と断ってくる。
つくづく、一定のペースで勉強できていることの強さを思い知らされる。
覚悟せよ

「行動の差は覚悟の差」という言葉を見つけてドキリとした。
今でもまだまだ腰が重くもっと軽やかにありたいと思っているが、私は行動のできない子供だった。絶対にこうしたほうがいい、こっちのほうが後悔しないと分かっていても動き出せなかった。ほんの些細なことから自分の人生に関わる重大なことまで、結局他人任せにしてしまったことが多く、ぞれは今でも後悔している。あの頃自分に足りなかったのは確かに「覚悟」だったと思う。
これ以上行ったら後戻りができないというラインを踏み越えられない。変化することが怖い。バランス良くあろうとして結局小さくまとまっていた。変化することへの「覚悟」、これが行動の差を生むのだと思う。
「塾に通う」ということ。それは学習面において、今までと同じではいられないということだ。なんとなく親についていってそのまま入塾となったから通ってるだけ。そんな気持ちでは何も変わらない。本当の意味で塾に通ってはいない。覚悟が無い限り成績に変化など起こせない。さあ、君にはその覚悟はあるか。
今日もいつも通りのことを

明日から中学生は2学期の中間テストが始まる。
本日を含めこの3連休をどのように過ごしたかが結果にモロに出ることだろう。
自習に来ている生徒の勉強の様子を見ていると、まずまずの仕上がりを見せている。私は聞かれない限りこちらから勉強のアドバイスをすることはあまりない。だから生徒の勉強の仕方はそれぞれ異なるが自習に来ている生徒の勉強内容はだんだんと似通ってくる。
まずはワークを周回するようになる。その合間に漢字や英単語などの暗記ものを覚えて塾の問題集を解く。プラスアルファできる子は教科書を読み込んだりしている。何も特別なことはない。手元にある教材をやるだけだ。
ギャーギャー騒がず、次々新しいものに手を出したりもせず、粛々と目の前のものに取り組む。ちゃんと勉強できるようになってくると、みんなこのパターンになっていく。教材なんて基本的にどれも一緒。しかしその習熟レベルに差があるだけだ。そんな私のイズムを受け継いでいるのかどうかは分からないけれど、結局当たり前のことを当たり前以上にやれる子が伸びる。
この瞬間にも差は開く

世間は3連休だがもくせい塾は通常通り営業している。中学生の2学期中間テストまで残り3日だ。今日から部活動も停止期間に入っているはずである。受験生は当然すでに教室に来て勉強を始めているが、他学年の生徒はまだまだ集まりが悪い。やむを得ないことでもあるが、これが意識の差ってやつだろう。
テスト2週間前から1日5時間勉強している生徒と全くしていない生徒、その差はこの2週間だけで70時間。定期テストは年間4,5回。少なく見積もっても年間280時間の差が生まれるということだ。こう考えるとどうだろう、それでもまだ
「効率の良い勉強法」
なんてものを求めようとするだろうか。もう断言してしまってもいいかも知れない、初めから効率を求めようとする人は勉強をしたことがない人だ。こうしたところで蓄積の差をどんどん広げられているのにそこには目を向けず、受験が近くなってから「勉強のやり方が分からない」とか言っちゃうのは「楽して稼げる仕事」を探すようなものだろう。確実に前に進む勉強のやり方は、「今、この瞬間」から問題集を開いて解き始めることだ。まずは日々の生活の中から積み上げていくこと。これに勝る「効果的な勉強法」はない。
カンニングの跡に対して思うこと

教室の机にカンニングの跡が残っていた。
机の端に小さな字で英単語が書いてあった。そこに座った生徒の子が見つけるまで全く気付かなかった。単語の内容的には中3かなぁ。字体を見るにおそらく今年の生徒のものではないと思う。消えずに残っていた。
もちろんカンニングは不正行為だけれど、私は「見つけたら注意する」くらいの感覚でいる。やっちゃいけないことくらいみんなさすがに分かっているし、それをしたときの代償を支払うのは自分自身だ。弊塾で行っている単語テストは公平なものであって公正なものではないので、そのあたりの責任は自分で負ってもらいたい。
変な話に聞こえるかも知れないが、実はそういう不正行為も「経験」だと思っている。もし今カンニングをして目の前のピンチを切り抜けたとしても、
「あの時ズルしちゃったな…」
という後悔の念が心に残ればそれはやがて「徳」になるはずだ。次に同じシチュエーションになったときに正しいほうを選ぶ指針になってくれればいい。反対に自分の行った悪徳をすぐに忘れてしまってそれを繰り返すようになってしまったら救いようがないが。もしもやるなら罪悪感はしっかり感じていなくてはダメだ。
完全に清廉潔白な人なんていないはずだ。
だから今のうちに清濁併せ呑んでおいて、「ルールだからダメ」という戒律の言葉によってではなく、自分の中の正義の言葉に従って動ける人間になってほしいと思っている。心の中に後悔の澱がたくさんたまっている人は、その分だけ正義を振う力を持てるはずだ。
あ、だからと言ってカンニングを肯定するつもりは更々無い。もし見つけたらブチ切れるのでそこんとこはよろしく。
成績が上がるサイン・下がるサイン

怖い話だが、テストの結果はそれが実施される前にある程度予想できてしまう。定期テストなら1週間前にはほぼ当てられるし、3日前にはそれは確信に変わる。現在中学生の中間テスト直前。私の中では予想がある程度出ている。今回は受験生の中に大きく成績を伸ばしてくる子が1人いるかな。その逆は...置いておく。
その判断基準となるのが、通塾頻度とその過ごし方だ。成績が大きく伸びる子は通塾頻度が高くなる。毎日来るようになったりする。これがマストであって、その上学習の密度が高い。この2つがそろうと成績アップのリーチだ。そして授業内でテスト対策問題を解かせた時の出来具合が良いと、それが確定へと変わる。
反対に通塾頻度が下がった、自習室でやっている内容が薄くなったという場合はほぼ確実に成績が下がる。自宅で学習できないから塾に来るわけで、塾への向き合い方がそうなれば当然の結果だよね。塾から施す指導は何も変わらない。変わるのはいつも生徒のほうだ。
そんな経験を持ってしまっているから、「あ、この子今回成績が下がるな」と感じた子には先手を打って「もっと勉強しなきゃダメだよ」というメッセージを出すのだが、難しいのが、直接言ってもなかなか伝わらないことだ。感情に負けちゃってる状態だからね。
なので実際に問題を解かせて、思っていたよりも自分ができていないことを実感させる。そうすると「ヤバいかも」と思える子は結構いる。しかしこれも必ずそうなるわけではなく、今回何人かの生徒に行ったのだが果たして結果は変わるだろうか。
居眠りはしないようにね

昨日はさすがに我慢できなくなってしまい言った。自習室で居眠りを繰り返している生徒がいることについて。全体に向けてね。
昨日話した内容は
・居眠りはそれを見ている後輩に悪影響を及ぼす。正直恥ずかしい。
・眠いなら自習室には来ないでほしい。
の2点かな。要は「自習室では居眠りしないでください」ということなんだけれど、こう伝えてもあまり刺さらないと思ったので少しだけ本心も交えて話した。
以前も書いたが、教室内でつい眠くなってしまうことは誰にでもあるだろうしそれは仕方ない。だが居眠りは癖になる。ダラダラしてしまう癖は周りにも悪影響を及ぼす。そういった意味で、弊塾の自習室に居眠りする生徒はいらない。
それなりに伝わったのか、その後身に覚えのある生徒が謝りに来た。また、この後の授業は非常にピシッとした空気になってしまった。みんな必死に問題演習をやってしまっていて、正直「なんだかなぁ」と思った。何か言われないと出ない必死さなんて借り物だからいらないのに。
謝りに来た生徒に、私は「全体に言ったことだから別に君が謝る必要は無い」と伝えた。これに対しては半分嘘だ。いや、嘘と言うより本当に大切なことを話してはいない。
本当の思っているのは、そんな謝罪しても「もう取り戻せないよ」ということだ。ダラダラと居眠りをしていた時間、それはもうどうやったって戻ってくることはない。そういう意味ではその子はもう「支払ってしまって」いるのだ。私のご機嫌を伺っている暇があるのなら1問でも問題を解いてここからの時間を無駄にしないようにしたほうがいい。受験まで残り140日なんだから。
ワークを失くした➂

さて、ここまでの話が私の経験談で、これらから学んだことや今の弊塾での対応を記したい。
まず、提出の必要に迫られてから「ワーク失くした」と言う生徒は勉強に対するプライオリティが非常に低い。このままでは成績は絶対に上がらない。失くしたことをテスト期間、それも塾でやらされることになってからやっと言い出すということは、失くしたことに気付いていないか、気付いていたとしても自分で対応しようとしなかったわけだ。それは「誰かがやってくれる」という他責思考の表れだ。まずはここを改善し、勉強を自分事と捉えられるようにならなくては学力アップの段階に入ることができない。
だから、こんなことで塾があれこれと汗をかいてはいけないと考えるようになった。塾は学習サービス提供の場であって、育児サービスは提供していない。それを手取り足取りどころでなく、手足そのものとなってやってあげてしまっていてはいつまでも子供に成長はない。
中国では一人っ子政策時代に「小皇帝」という言葉が生まれたそうだ。甘やかされて育てられ、自分が特別な存在であると思っている人のことだ。塾の生徒を小皇帝にしてはいけない。いや、私がやっていたことは小皇帝どころか、「小神様」だったのかも知れない。足が汚れてはいけないと、神輿から降ろすことなく目的地へ運ぼうとする。授業料という「ご利益」のためにそんなことをやっていたかと思うと、申し訳なさと恥ずかしさで死にたくなる。
弊塾では「○○失くした」に対して一切関知しない。「ワーク失くした」「へーそれは大変だね」である。まず失くしたからどうなんだとすら言えないのは、文字通り「話にならない」。そこでアドバイスを求められればコピーの話くらいはするかも知れないがコピーを用意してあげることもない。テスト範囲40ページほどのコピーを行うのは1時間程度かかる。貴重な講師の人工をそんなことに割けない。
そして失くしたことをちゃんと「叱る」。自分の人生に関わる進路、その為に必要な道具を無くして何も思わないのでは成長しない。ましてやそれを臆面もなく「なんとかしろ」とばかりに言ってくるのは成績を上げる上げない以前の問題だ。叱る、そして反省を促して再発防止に努めさせる。だからこれで辞めていく生徒も結構いた。以前、学校の教科書も持って来ず塾のものを毎回借りていて、私が作って与えていた板書ノートも「失くした」とケロリと言ってきた生徒にブチ切れだことがあるが、その生徒は翌週辞めた。
おかげさまで現在弊塾には神様はいない。みんな追い出しちまったからね。今は現世利益のために努力する人間だけの集団になっている。神様になりかけていた生徒もいたが、人間界に引きずり下ろした。今ではその子も足の裏は真っ黒だ。
ワークを失くした➁

さて、テスト期間中に自ら動こうとしない生徒のお世話に奔走する講師たち。その講師たちへ頭上より振り下ろされる
「ワークを失くした」
の一撃。もうオーバーキルである。
それでも健気な我が同胞たちはどうしていたか。まずは本当に無いのかの確認だ。もう一度自宅と学校、そしてカバンの中を探させる。探して来るよう伝え翌日、すぐに動かない子もいるので翌々日、さらに次の日としつこく結果を聞き、本当に無いようならば他の子から借りたワークのコピーを取って渡し、とりあえずそれで進めさせる。その際
「学校の先生に正直に失くしたことを言ってコピー提出の許可を得るんだよ」
と伝える。ただしこれは生徒が実際にやるかどうかはもう分からない。塾が代わりに学校に電話を掛けてお願いすることはできないからだ。学校の先生もそんなの戸惑うだけだ。
その後ちゃんと提出したかの確認を一応はするが、全員「出した」とは言う。だがもうお分かりの通り、その真偽は通知表が出て学校の保護者面談があり、保護者の方が学校から事実を聞くまで分からないのだ。
こうして焦土と化したテスト期間も終わり、とりあえずあと塾でできることは、テストが終わったら新しいワークを手に入れるように生徒に伝えることだ。たまに学校の先生が配布した余りをくれる場合もあるが多くの場合は購入し直すことになる。購入ができない場合はコピー提出の許可をもらうしかない(→冒頭に戻る)。
ただし、この状況になった場合の生徒が新しいワークを手に入れて他の子と同じように勉強できるようになることはほとんどなかった。その前に
「塾に通わせているのに成績が上がらない」
と、その子の保護者から退塾を言い渡されてしまうからだ。こうして私たちの「ワーク失くした」に関わる一連の戦いは幕を閉じる。
ワークを失くした➀

今日の文章は、心ある保護者の方なら身の毛のよだつ話として最後まで読み進めることはできないかも知れない。
昔働いていた塾では、
「ワーク失くした」
と生徒が言うのをたびたび聞いた。
当時、定期テスト前に学校の提出物が終わっているか塾がチェックしていた。せざるを得なかったわけだ。今考えると恐ろしいが、それが塾の「面倒見の良さ」だと思っていた。今ならこれは大きな勘違いだと言えるのだが。
まず、テスト範囲の提出物が終わったかどうかも本人が把握できていない。だから生徒からの報告を待っていては埒が明かず、学校のワークを塾に持ってこさせ、私と担当講師でテスト範囲表を見てチェックしていた。なんとこの間、生徒は何もせず隣で座ってるだけ。
で、そういう生徒は自分ではやらないから授業外で塾に残して、手の空いている講師に頼んで隣に付いてもらったりもして期限に間に合わせるのだ。提出期限はテスト当日なことが多いので、テスト勉強の期間はそれだけで終わる。そして提出させるのが目標だから答えを写させたりするだけ。
今になって思う、これは一体なんの時間だったのか。誰も幸せにならないのは、少し考えれば、いや考えるまでもなく結果を見ればすぐに分かったのに。当時の私はバカだった。
この過程で冒頭の「ワーク失くした」というセリフを聞くのだ。もう笑えてくる。
どこまで差をつけられるか

今日から10月だ。今年も半分が過ぎた。
中学生の2学期中間テストまで残り2週間となった。テスト範囲把握の為、各学校の生徒はテスト範囲表が出たら教室に持って来て下さい。把握できない場合、こちらは「なんとなく」でやらざるをえない。生徒には当事者意識を持って行動してもらいたい。
テスト範囲の全てのワークが1周終わった生徒が出てきている。これがテストで良い成績を取る生徒の「標準形」だ。このくらのスピード感が無くては上位を目指すことなんてできない。もしもまだ何も手を付けていない生徒がいるならば、この瞬間から勉強をはじめなくてはならない。上位層とはすでにワーク1周分の差がついている。それまでの授業の受け方や日ごろの予習復習も含めればその差はもう絶望的だろう。
しかし今始めることができれば、明日始める生徒よりも1日分の差ができる。勉強は「今」始めるしかないのだ。今日も教室を開けるなり受験生を中心に生徒たちが続々と自習に来ている。差は開くばかりなのだから。
【塾生のみなさんへ】お土産をいただきました!


修学旅行に行った生徒たちからお土産をいただいた。ありがとうございます。
置いておけるものはポストの横にあるので欲しいひとはどうぞ!生菓子はその時いる生徒に配っちゃう。あと私個人にいただいたものもあったので、それはありがたくいただきました。
板書を写す

やはり学力に大きく関わってくると感じているのが「再現性」だ。問題をただ解けるのではなく、お手本と同じように解けるか。上手に真似ができる子は上達も早い。
そのために求められる能力は、板書を写すことで養えると思っている。授業の板書をきちんと写すことができているか。たしかに授業で作られる板書の内容は教科書にあるものなので、教科書があれば必要ないと言えばそうかも知れない。最近ではプリント穴埋めや映像を利用した授業など、板書を写させない授業形態も増えてきた。
しかし情報を残す意味以外にも、先生の板書を真似して書く作業は「型」を取り入れることにもつながるのだ。板書は教師の作品。構成や使う言葉、色分けまで含め作成者の思考も踏まえて表現されているものなので、それを写すということは先生の思考パターンも写し取ることにもなる。こうして自分の脳に先生の考え方を写し取れた子は学力が伸びやすくなる。
ボーっとしていたり舐めていたりして、授業中に手を動かさず板書をきちんとノートに写さない子は、知識はあるかも知れないが先生の思考は写し取れていない。だから問題を解く時にイチから自分の解き方の理論を構築しなくてはならない。授業中に頭を働かせることなくただノートを写すだけでは効果は薄いが、きちんと内容を咀嚼した上てノートも写す。そうすることで先達の手法を真似することができるようになり勉強が上達していく。
早目の準備が勝利の条件

中間テスト3週間前になり、
「授業の小テストは先に進めたほうがいいですか」
とアドバイスを求めてきた生徒がいた。
弊塾では定期テスト3週間前からはテスト対策が行えることを目標に指導を進める。この生徒も英数ともに予習がかなり進んでおり、もうすぐ今年度の学習を終える。だからいつでも中間テストの為に復習に戻って来られる状況だった。本人もちゃんとそのことが分かっていたのだろう、ちゃんと自己管理ができている証だ。
私は先に進まないという判断を下し生徒に伝えた。
「そのかわり中間テストの範囲の2周目の小テストを準備して」
テスト対策期間に入っても塾内のシステムは動き続ける。こうしてテストに向けた勉強がはじまる。この時期から準備を始めてテストまでに何度も繰り返し学習できれば成績は必ず上がっていく。
作者の次回作にご期待ください

弊塾の生徒には学習記録をつけてもらっている。自習であれ授業であれ、塾に来た日は学習した内容とひとこと感想を書いている。
このねらいはいくつかあって、まずは勉強を点ではなく線にすることだ。たまに何度も同じ場所をやっている生徒がいる。繰り返すのは大切だが、無計画に同じ場所ばかりやっていても上達はしない。前回やったこと、その時の様子を残しておき次の学習時にそれを踏まえた計画にしてもらうのだ。
次に1日の学習時間の密度を上げること。無計画で勉強時間を過ごすと、いくらでもサボることができる。机に座っているだけで時間が経ってしまうからだ。だから学習に入る前に計画を立ててもらい、それをこなすように過ごしてもらう。To Doリスト型の計画表なので、どんどん処理する感覚で進めれば勉強の密度も高めやすいはずだ。
そして自分の勉強に対して自覚的になること。ひとこと感想を書いてもらうのはまさにこのためで、自分の勉強を「自分のもの」とできた子から学力は伸びていく。だから1日の終わりに自分の過ごした時間を振り返り、それがどうだったのかを言語化してもらっている。
つまり、生徒の学習記録シートを見ればその生徒が今後伸びるかがすぐ分かるということでもある。伸びる生徒のシートは「完璧な報告書」であり、それ以上に生徒自身の「意志表現」になっている。今まで見て来た成績の良い・学力の高い子のシートはそれ自身がルポルタージュであり、私小説のようでもあり、また演説のようでもあり、大変読み応えがあった。
マンネリした内容の薄い報告などいらない。勉強に本気であることが一瞬で分かるような、そんな学習記録を読者は待っている。
自分で動ける子に

自学力は質問力とセットだ。自学力を身に付けるには「質問」ができるようにならないといけない。自学は能動的な行動だ。受け身で待っているだけで身に付くものではない。
「うちの子、自分から聞きに行くことができないんです」
という話をたびたび聞くが、これは「ウチの子の自学力を奪って下さい」と言っているようなものだ。突き詰めれば「自分から聞きに行けない」から「分からないところを『お迎えに行って』あげてほしい」ということだろう。そうすると生徒の能動的な行為を引き出すことにならない。結果生徒はどんどん受け身になり、隣で付き添っていないと何もできなくなっていく。これでは本末転倒だ。
だから私は、上のようなリクエストがあっても
「では自分で聞きに行けるようにならないといけないですね」
と言うようにしている。突き放したように聞こえるかも知れないが、これが自学力を身に付けるということだ。
「面倒見がいいです」を履き違えてはいけない。面倒見の良さは、生徒の召使いとして仕えることではないし、ヘルパーとして介護してあげるものでもない。生徒の先々の人生を見据え、生きる力を身につけさせてあげることだ。私は生徒を愚かにさせるつもりはない。それまでは目の前に運ばれた食事だけをしていれば良かったかも知れないが、それではすぐに壁にぶつかる。自分で手足を伸ばすことを学んでもらう、それが弊塾の存在意義だ。
終わった時にそれを言えるか

日曜に演劇を見て来た。
出演者の方がこんなことをおっしゃっていた。
「終わった時にちゃんと『やりきれた』と言えるように臨みたい」
そうおっしゃる通りの素晴らしい舞台だった。
どんなことでも「終わった時」のことを想像するのは大切なのかも知れない。その時に後悔の無いように。受験生ならば受験が終わった時に、それ以外の学年の生徒でも定期試験が終わった時に、もっと言えば「今日の終わり」にちゃんと「やりきれた」と言える勉強をしているか。まだ終わりを意識するのは難しい年代の子たちにこれを伝えるのは難しい。経験が伴わなくてはできないことだから。
しかし業務が終わって、「おわりだよ」と言っているのにまだ机にかじりついている子たちにはその空気を感じることがある。終わりのチャイムが鳴る前から帰る準備を始めて物音をガチャガチャ立てている子もいる中、そういう子たちは「今日をやりきるんだ」という意志をまとっている気がするのだ。きっとそんな子たちの意識は加速して、普段よりも何倍も濃密な時間を過ごしていることだろう。(でも時間が来たら終わろうね)
自分は大丈夫?

同じ科目ばかり勉強してしまう子がいる。特に「数学」と「社会(歴史)」にその傾向が強い。
おそらく数学は問題が解けたときの快感を求めて、社会は答えを知っている安心感を求めてそればかりになるのではないだろうか。どちらにせよそれでも勉強した気になれるのでこの現象が発生する。それ以外の科目ではあまり見られないのが興味深い。科目ごとの解答する労力も影響しているかも知れない。
それで今まで勉強して来なかった子がそうなるのはまだいい。ゼロがイチになったことは喜ばしい。しかし受験生だと話が変わる。得意科目ばかり勉強してしまう受験生はまだまだ勉強と向き合えていない。受験は複数科目の総合力勝負になる。足を引っ張る科目があるとかなりキツイ。得意科目ばかりやってお茶を濁している場合ではないのだ。
受験生で苦手科目から目を背け、好きな科目ばかりやっている子は冬くらいになって(時には年明けになって)足を引っ張っている科目をどうにかしようともがきだす。しかしそれではもう遅いのだよ。早目に自分の「逃げてしまっている心」に気付かなくてはならない。
ノウハウを捨てよ、回り道をしよう

私は中学高校生時代に勉強のやり方などアドバイスを受けたことは無かった。学校で予習のやり方の説明を受けたことくらいはあったけれど、テスト勉強や受験勉強は自己流だった。だからその中で自分なりのやり方を試行錯誤し、たくさんの上手くいかないことを経験した。
そんなだから、弊塾に通っている生徒たちにも勉強の指示をあまりうるさくあれこれすることはない。塾のルールを守ってくれればその日生徒がやっていることに口を出すこともほとんどない。かなり放任だ。
「勉強のやり方を教えてください」
と保護者の方から言われることは多い。自分の中にもそれなりにノウハウはある。しかし今までの経験上、それをそのまま生徒に伝えてもほとんど効果は出ない。なぜなら「やり方」を教えても上辺だけの真似事になってしまうからだ。
結局、私が勉強をして身に付いた教訓は「どんなことでも上達するには試行錯誤が大切」ということだった。あれこれ失敗して結局一番効果的な方法を探る過程にエッセンスはあるのではないか。だから経験の無い子に最短距離の進み方を教えても意味がない。結局その距離をノロノロと歩くだけになる。自分のやり方を試し、失敗し検証して次の策を練っていく。その中で「なぜ効果が上がるのか」を自分の言葉で説明できるようになることが勉強できるようになるには必要なのだ。
もちろん生徒が勉強のアドバイスを求めてきたら答える。具体的なやり方も示す。しかしこれは生徒が自分の道を歩き出した証拠でもあるのでやっている。そういう子にするアドバイスは効果が出る。
回り道をしたらいい。その道を用意してあげることこそが「勉強のやり方を教える」ことなのだと思う。
アゲハチョウ

子供の頃、アゲハチョウを飼ったことがある。飼ったと言ってもそんな大層なものではなく、見つけた幼虫をもと居たみかんの枝ごと虫かごに放り込んだだけのものだったが。アゲハチョウの幼虫は危険から身を守る時に角を出して威嚇する。それはどことなく柑橘系の匂いがした。
さてその幼虫だが、持ってきた枝に付いていた葉をあっという間に平らげた。私ははじめその食事風景が面白く何度か葉を放り込んでは眺めていたが、やがてそれにも飽き次第に虫かごを覗くことは無くなっていった。
2,3週間ほど経った頃だろうか、幼虫はサナギになっていた。それを見て驚きはしたが、幼い私は動かないサナギにもすぐに飽きてまた放置した。しかしさらに数日後、サナギはついに蝶になった。
20センチ四方ほどの小さな虫かごの中で羽をバタつかせている蝶を見た私は「幼虫から成虫へと育て上げた」ことに興奮し、再び蝶を観察した。しかし私の育てた蝶は、自分の知っているアゲハチョウよりも一回り小さく、モンシロチョウほどの大きさしかなかった。おそらく幼虫期に与えたエサの量が足りなかったのだと思う。
その事実にショックを受け、私はそうしてしまった罪悪感から逃れるようにその蝶を逃がすことにした。自宅アパートの3階の窓から健気に飛んでいくアゲハチョウを見て私は「育てる」ことについてはじめて何かを思った。
育てるとは時間と手間のかかる作業だ。育てる側に愛情が無いと、蝶の羽は大きくならない。
学生時代に何を学んだか

先日、母校の応援団を特集しているテレビ番組があり視聴した。歴史ある応援団唯一の3年生の引退までを追ったドキュメンタリーだ。
当時と変わらない部分に対しては懐かしさやノスタルジーも感じつつ、私の在籍していた頃との違いも楽しめた。もっとも私は不良高校生で母校への帰属意識は希薄だったので、自分が知らないだけで当時もそのような気風はあったのかも知れない。
見ていて思い出したことがある。番組の中で応援団長への印象を生徒たちにインタビューしているのだが、皆一様に「尊敬できるすごい奴」という答え方をしていた。これが番組製作側の恣意的な編集なのは重々承知として、ひとつのことに打ち込み、貫くことを「カッコいい」とする風土は当時からあったような気がする。
応援団なんてバンカラの最もたるイメージで、ともすれば時代遅れの「ダサい」ものだろう。しかし私は応援団や「愚直でも続けられる人」をカッコいいと思う。そしてそう言える目を高校時代に養えたのは良かったと思っている。カッコいいはひとつじゃない。そして見た目だけでなくその背景にあるものがカッコいいんだ、と。
こんな不良品だが、そういう多様性への意識を育めた母校には感謝している。
信じる心

その生徒は、進路面談の際に私からの提案を「嫌だ」と突っぱねた。
私が提案したのは、その子の偏差値からすると「妥当な」学校であり、むしろ持っていた通知表の成績からすると「少し背伸びした」学校ですらあった。私の指導力ならそのくらいはなんとかなる、と思っての提案だった。
その子は、
「自分はそんな学校に行くような人間じゃない」
と言った。
当時の私は、その子の言い分をただの自意識過剰な駄々のように感じていた。代わりに本人が挙げてきた志望校は、その子の成績では過去に誰も合格者は出ていなかったし、学校からもそう言われていた。受験まで残り8ヵ月、偏差値も通知表も全く届いていない状況で、どうやって受かるんだ、と。
そのくらいの時期だと、まだまだ「夢を見て」いる生徒も多い。私の反応は冷やかだったと思う。以前まで勤めていた塾では塾の名に傷を付けるわけにもいかないのでそんな受験を認めることはしなかった。「全員合格」がモットー。偏差値も通知表も届いている安全圏の受験を。保護者も交えて話し合った結果、併願戦略を練った上で本人の希望する学校を受験することになった。私はその子が受験に失敗し併願校へ通うことになる未来を何度もシミュレーションした。
結果、私の考えは全て間違いだったことになる。
その子はその後偏差値を更に7ポイントも上げ、通知表の大きなビハインドも覆し第一志望校に合格した。弊塾から出た逆転合格者の第1号だった。学校の先生も大変驚いていたそうだ。某中学校の過去卒業生データには、こうしたイレギュラーがいくつか存在しているはずである。
私はこの時の記憶を、ご両親の言葉と共に思い出す。ご両親はこの進路面談の際こうおっしゃった。
「本人の意思を尊重したい」
かなわねぇなぁ、と思う。
焦ってる?

今日も学校から帰って来るなり、高校受験生たちが教室に来て勉強を始めた。私も生徒の暗記チェックや質問対応に回っている。
秋は、受験生たちの目の色が変わってくる時期だ。私が毎年「あ、本気になったな」と感じるのは、生徒たちの教室へ来る時間帯の「幅」が狭くなった時だ。
近隣の中学校に通っている子たちだから、学校が終わる時間は同じ。自宅もそう離れているわけではない。だから学校が終わって一旦帰宅してからすぐに教室に来るようになると、みんな近い時間帯に集まるようになるのだ。ゆえに最初に来た子と最後に来た子の時間差が縮まる。それまでの「少し休憩してから…」という意識の子がいなくなってくると起こる現象で、これはいよいよ本気だなと感じる。今日はその差が30分も無かった。
この記事を見ている保護者の方で、現在まだ受験生のお子さんが通っている塾に出かけておらず自宅いらっしゃる場合、申し訳ないがお子さんは弊塾の受験生たちには絶対に勝つことはできない。なぜならこの行動は私が指示したものではなく、生徒たちが自ら起こしているものだからだ。夏休みから長時間学習を始めて体を慣らしてきた。それに伴って意識も高まってきた。そうした仕込みの無い秋を迎えてしまうと、今でも家でスマホをいじっているような受験生活になる。
本気の生徒は行動が変わる

最近は平日に学校説明会を実施する高校も増えた。休日は教員を休ませるという働き方改革の影響だろう。
平日の今日、夜から実施される学校説明会に参加する生徒がなぜが塾に来ていた。聞くところによると、これから説明会に参加してまた教室に戻ってくるそうだ。
説明会の前に誰よりも早く教室に来たその子は私の前で暗記のチェックテストを受けた後、慌ただしく説明会へと向かって行った。やろうと思えばこれくらいの行動はできるということだ。本気が見られて嬉しく思う。体調には気を付けて精一杯受験生をやっていってほしい。
教室内での居眠りについて

もちろん体調面のことは考慮するが、それでもやはり教室内での居眠りを「良し」とはできない。なぜなら「周りの人の迷惑になる」からだ。
自分が一生懸命に頑張っている横で、フザけた態度の人がいたらどうだろうか。「やる気がないなら視界に入らないでほしい」と思わないだろうか。教室内での居眠りとはそういう行為だ。頑張りたいと思っているがどうしても体調面がすぐれなくて舟を漕いでしまうというくらいならまだいい。机に突っ伏して堂々と眠っているのはいかがなものか。それは居眠りすることを「許された」人間がすることだろう。私はそれを認めていないし、少なくともそれを見た私のやる気は削がれる。正直言って「視界に入らないでほしい」だ。
以前は苛烈にブチ切れて帰宅させていた。いろいろ考えて今は注意のみに留めているが、こういう生徒は何度注意しても治らない。自分が他人に迷惑をかけている自覚がないからだ。これからも基本的には何も言わないが、何も言わないのと何も思わないのは違う。心当たりのある生徒は私の機嫌を損ねないよう気を付けてほしい。
夏期講習の振り返り➂

中3第4回北辰テストの結果が出た。これを踏まえて夏期講習の最後の振り返りをしておきたい。
今回の北辰テストで初参加の生徒も多かったので塾内偏差値の変動はアテにならないが、個人で見ていくと継続的に受けている生徒で伸びたのが半分、現状維持が半分というところ。明確に下がった生徒はいなかったが、大きく伸びた生徒もいなかった。
毎年そうだが、科目ごとに見ると伸びた生徒は理社の成績の変化が大きい。今年はだいたい偏差値が5ポイント前後、最大で11ポイント伸びている。今まで暗記をしっかりやってこなかったというのが理由だろう。理社の学習自体もあまり触れていなかったのかも知れない。
他には国語の成績が伸びている生徒が多い。夏休みの課題に毎日読解問題を入れていたこと、漢字テストを行っていたこと、そして即効性の高い古文と作文の指導があったことが原因と考えられる。
数学や英語(と国語)は即効性がが低いので結果は人それぞれ、全体的なトレンドはつかみにくい。英語が伸びた生徒もいればやや下がった生徒もいる。特に数学は凡庸な結果に終わってしまった。強いて言うならば数学の大問1の問題4つ目までは塾生の正答率100%で通過できたことは明るい。基礎固めができたので、秋以降の伸びに期待したい。
総括すると当たり前の結論になってしまうが、毎回の授業、課題、そしてテスト道場にしっかり取り組んでいた生徒は成績が上がっている。課題をやり切っていない、テストに合格していない、自習せずに帰っていた生徒は伸びていない。対照実験のようになってしまって嫌だが、夏期講習に一定の効果は見られる結果となった。
受験生たちはここからがプレッシャーも大きくなり本当の戦いになっていく。指導はもう少し続くが、受験勉強はまだまだここからだ。夏に振るわなかった生徒はもう一度自分の進路についてよく考えてて行動に移すこと、伸びた生徒も手を抜くとこのあと下がっていくので気を抜かないようにいくことを期待したい。
塾が防波堤になるべき案件

今の弊塾にはいないが「指導に口を出して来る系」の保護者がいる。偏見だが、そういうご家庭の生徒の成績はほとんど上がらない。なぜなら親に忍耐力がないからだ。
我が子にはあれをやらせて下さい。やったらテストをしてチェックしてください…
昔働いていた職場では「じゃあ自分でやりなはれ」と言いたくなるほど指導の指示をされる保護者の方もいた。きっと子供が「言うことを聞かない」状態になっていてフラストレーションを溜めていたのだろう。だから塾の先生を通じて自分の言うことを聞かせたかったのだと思う。
しかしこれは悪手だ。まず子供が親の「言うことを聞かない」のは、すでにガミガミ言われ続けて耳を塞いでしまっている状態だからだ。それを直さずに別の人を通じて言うことを聞かせようとしたって何も変わらない。
結局そういうご家庭は、生徒指導をはじめても成績に変化が見られる前にしびれをきらして退塾してしまう。生徒が話を聞かない状態に凝り固まってしまっていると、それを解きほぐす作業から入らねばならずそれなりに時間がかかる。自分で結び目をぎゅっとしてしまったのに、それをほどくのを手伝っている人に「早くして。ねえなんですぐできないの?早くしてってば」って言っているのだ。
子供は自分とは別の人格だ。それに対し要求を即時に通しその通りに動かすことなどできない。そこで我慢できないと「ガミガミ」が出てくる。なんとかしたいと思う親御さんの気持ちは汲みたいが、塾に入れても親がその姿勢のままだと変えることはできない。矛先は塾へと向き、指導に対してもあれこれ口を出したくなっちゃうのだろう。結局子供をできなくさせているのはその親自身なのだ。
指導に注文を出されていたはじめの頃、私は全部引き受けようとし、できる限り言われたままやろうとしていた。言われた通り生徒の学力に合っていない教材を使い、言われた通り時間的・能力的にできないテストを課し、言われた通りできるまで自習に残ることを強制しその日の業務終了まで座席に座らせ続けた。それがサービスだと思っていた。それで結局生徒を苦しめてしまっていたのに。もっと早く気付いて、今の姿勢で親と対峙すべきだった。私が強制すべきは生徒ではなく親だったと今なら言える。
その時の子供の「また辛いことをさせるの?」と言いたげな暗い表情は忘れられない。
自ら考えて行動する

今日も教室を開けて間もなく、受験生たちが自習の為にやってきた。
座席に荷物を置くなり、すぐに私の元にやってきて
「英語の教科書のテストを…」
「社会の用語集のテストをお願いします」
と、それぞれ希望のテストを申し込んでくる。土曜の前半は私も時間があるので生徒もこのタイミングを狙ってくる。先ほどまで相手をしていた。
再テストは塾のルールなので受けにくるのは当然だが、社会や理科のテストなどは私がやらせていることではない。どうすれば学力を伸ばせるかと自ら考えてのことなのだろう。これぞ自学力。もちろん受験が近いというプレッシャーのもとでの振る舞いに過ぎないけれど、自分で考えて行動できる子はどんな道に進んだとしてもきっと大丈夫。
勉強を教えるのではなく、勉強の仕方を教える。一見遠回りだが、これができるようになると一人になってもずっと遠くまで歩いていける力になる。
日本語をしっかり使う

先日、ある生徒の東部地区テストの結果を見せてもらった。英語の偏差値が70を超えた。
英語は努力の科目だ。かけた時間に学力が比例しやすい。だから真面目に勉強しているのに英語の成績がそれほど伸びない場合、普段使っている「日本語」に原因がある。日本語は主語や目的語を「省略」しても話が通じるし、時制もあいまいでなんとかなる。しかし英語ではこのあたりにきちんとルールがある。だれが、いつ、なにを、どうしたということをしっかり表現する必要がある。
だから英文を書く時に「日本語のあいまいさ」を持ち込むと失敗する。日本人ならば英語の問題を解く時でも日本語で考えているだろうけど、普段使っている日本語がふにゃふにゃだと正解できない。普段から主語を省略してしまったり、単語での会話の癖がついていると英語で伸び悩むのだ。ここに英語学習の落とし穴がある。
塩対応

入塾を検討して面談に来られる保護者の方と生徒には、
「ウチは放任です」「自習はほったらかしにします」「自分で勉強してもらいます」
などのネガティブにも取られかねない言葉を使って自塾の説明をする。なぜかと言うと「覚悟」をしてもらうためだ。
たしかに
「面倒見がいいです」「きちんと見ます」「分からないところは徹底的に教えます」
と伝えたほうが耳障りが良くて聞いているほうも安心できるだろう。しかしそう言われて「じゃあ塾に全てお任せすれば勝手に成績が上がっていくのね」と期待されてしまうと困るのだ。塾は学習サービスの提供であって子育て施設ではない。預けるだけじゃ勝手に育つことはない。
ほとんどの塾に言えることだと思うが、「授業の時間」以外で生徒に塾のスタッフがつきっきりになることはまずできない。塾運営で最もコストがかかるのが人件費。もしも自習などもつきっきりになってくれる塾があるのなら、その費用も料金に含まれている。つまり「面倒見がいい」にも限界があり、それは保護者の方が期待しているよりもずっと低いものになる。あくまで塾の言う「面倒見がいい」は料金の発生する授業の中でのみなのだ。だからなんでも手取り足取り全部やってもらおうと思っていると痛い目を見てしまう。
その点、弊塾のように初めから塩対応だと期待を上げ過ぎることはない。成績を上げるのはあくまで生徒本人。本人の努力なしに伸びることは無い。そしてその努力をさせるのは保護者の方である。その上で、塾が学力を伸ばすサービスを提供する。甘言にご注意を。こうした知識が無いと、期待して通わせたのに成績は下がる一方で
「でも子供が楽しそうに通ってるから...」
などと、変な理屈で臍を噛むことになる。だったらゲームソフトでも買い与えればいいのに。
弊塾は売上のために甘いことなど言わない。不親切な塾だと切り捨てられるならそれも止む無し。覚悟を持ってやってきてくれるご家庭に、全身全霊を持って指導させていただくだけだ。
負けず嫌いでしつこい

勉強に必要な要素は「国語力」「負けず嫌い」「しつこさ」だと思う。
特に負けず嫌いやしつこさなんてのは、その子の性質にも関わっているのでもしかしたら才能と呼べるしろものかも知れない。
昔、浦和一女に合格した生徒が、自分がクラス委員に慣れなかったことを非常に悔しがっていた。投票で負けてしまったライバルに対し、「私のほうが勉強できるのに…」と言っているのを聞き、なんとなくその子の学力の一端を垣間見た気がした。その子は今後人の部分が育てば、立派なリーダー足りえるだろう。負けず嫌いというのは競争である学歴において強力なモチベーションになる。
また、越谷北に行った生徒は、私の暇を見つけるたびに何か暗記したものを持って来てはチェックを申し込んできた。自分の満足のいく出来でなかった時は「もう一回、もう一回」と繰り返しを希望する。こちらが「もういいから」と音を上げそうになるくらいだった。
こういう泥臭さのようなものが学力を押し上げる。負けず嫌いでしつこい、勉強においてこれらの言葉は「誉め言葉」なのである。
文武両道って時間をかけた準備が必要だ

これは言語化するのが非常に怖いのだけれど、子供に突然「文武両道」を目指させるのは非常にリスキーだと思っている。
文武の「武」からスタートするとまず上手くいかない。塾に来る生徒で「文武両道にさせたい」ご家庭は、たいがいすでに何かスポーツに力を入れていて成績が下がったか、受験が近くなったかでやってくる。
「スポーツを今のペースで続けながら勉強も頑張らせたい」
と言って。
たしかにそうなれば理想なのは分かるけど、生徒のやる気をはじめとしたリソースはスポーツにほぼ持っていかれている状態だ。生徒自身もそこに自負を持っていることが多く、今更苦手な学力を伸ばしてやろうなんて思っちゃいない。その状態を崩さずにどうやって「文」を育てることができるだろうか。こういう時たいてい勉強に割ける時間は人より少ない。勉強だってそのスポーツに掛けてきたのと同等の時間が必要だ。片手間にできるようになるものじゃない。
「○○君は勉強も運動もできる(からウチの子だってやればできる)」
とおっしゃる保護者の方も結構いるが、それは「入口が違う」。そういう子は早い段階で勉強の土台ができている状態でスポーツもスタートさせている。スポーツに全振りしちゃった後ではその子と同じにはなれない。それはゲームでレベルアップボーナスを筋力のステータスを上げるのに使いまくったキャラを今から魔法使いにするようなものなのだ。
子供を文武両道にするには、結果が出る学年になる前、そう、小5くらいまでにある程度の学習習慣と学力を身に付けさせておくことから始めるのがポイントだと思っている。これを過ぎてから本当に勉強をどうにかしたいのなら、もうちょっとリソースを開けるために犠牲を払ってもらわないといけない。こんなことを言うとある層の人たちからは確実に嫌われるだろうけど。
本気じゃなければ泣く資格など無い

受験で志望校に不合格になったとき、君は泣くだろうか。
そして、その涙は何からくるものだろうか。
「目指していた道が閉ざされる悔しさ」からか?それともただ「自分が拒絶されたことで受けるショック」なのか?
この仕事をしてきてたくさんの受験を生徒と共に迎えた。臨まない結果だってたくさんあった。その時に泣いている生徒を見て、本当に目標に向かってずっと頑張ってきた子の涙はこちらに訴えかけてくるものがあった。そんなときは自分の不甲斐なさを痛感し、ただただ痛みだけを感じてきた。おそらく私は、そういう記憶を自分の受験指導に対する心構えにしている。だから私は受験を侮らない。
だがしかし、直前まで勉強をずっと逃げ続けているような子の涙は申し訳ないが響かない。それは本当の悔しさではないと感じてしまうからだ。
不合格を経験したどんな子でも、縁のあった学校で笑顔になってほしいと願っている。願ってはいるが、受験の傷をバネにしてそこで更に頑張れる子だけが本当に笑顔になれるのだとも思っているのだ。学習の指導者としてこんなことを言うのは失格かも知れないが、私は、自分の指導する生徒たちにはもちろん全員に望んだ道を歩んで欲しいが、もしそうでなかった場合は、私の琴線に触れる涙を見せてほしいと願っている。つまり中途半端はいらない。本気だけが見たいのだ。
暗記を続ける

「暗記」は辛い作業だ。地道だし孤独だし覚える時はストレスも感じる。できればやりたくないという生徒もいることだろう。だからこそ、暗記作業をきちんとやる生徒は他を出し抜くことができる。暗記をちゃんとやる子は勉強が孤独であるということを知っている。それを知った上できちんと向き合おうとする戦士だ。誰かが隣についていないと何もできないようなお勉強ごっこをしている者とは覚悟が違う。
弊塾では中3の夏休みにある程度の量の暗記作業を課す。他の優秀な塾に比べればたいしたことないが、それまでの学校生活では経験したことの無かった量だろう。ここで生徒たちは、受験生としての土台を鍛え上げることになる。チェックテストをすると慣れるまでは不合格を連発することになるが、それでも食らいつく子は夏が終わる頃には見違えてできるようになる。たった1ヵ月ほどで人は変わる。
ここで身に付けた暗記作業へのコツ・暗記力はこの後受験勉強をしていくときに学力を支える大きな武器となり、高校に入学してからも怒涛の知識のシャワーを受け止められるようになる。つまりは一生ものの力になる。
今年の夏に行った理科社会の暗記テストの残りを「夏が終わってからも個人で進めてテストを受けにおいで」と伝えてある。まあそう言っても多くの生徒はやりに来やしないが、中にはきちんと継続している子たちもいる。夏に暗記の効果を実感できたのだろう。1ヵ月で変化を見せた子たちがこのまま続けていけば、受験まであと数か月であっても、この先まだまだ進歩していくことだろう。
だから私にできることは、この孤独な作業を続けている戦士たちをテストという形でもって労い、その成長を祝福してあげることだけだ。
夏期講習の振り返り➁

授業内容に関してはほぼ例年通りに行った。5科目中1から中3の1学期までの復習、国語は現代文・古文の読解法、文法・作文の解き方講座。英語は文法の解説を厚めに行いその中で受験テクニックをしこたま仕込んだ。数学も苦手範囲を中心に全範囲の基礎~標準問題の解説。理科と社会は基礎事項の確認。理科は計算や実験考察問題などの解法も比較的多く触れることができた。
今年はそうだったのだけれど、集まった生徒の学力差が大きい場合、そのターゲットの絞り込みが難しい。なので私は基本的には「超基礎」の指導を行う。ついて来られない生徒が出ないように、そして高学力層であっても基礎学力が盤石な生徒はほぼいない。私が出会った中でも過去に4人くらいだ。だからそういう子にも絶対に刺さる授業となると自負している。
勉強が苦手な子でも分かるように、そして得意な子を退屈させないようにするのは苦労するところだが、授業の最中に生徒の表情を見ながら修正を加えて変更していくライブの楽しさでもある。
ここには勉強しないという選択肢はない

弊塾は勉強をやらない生徒には厳しい。これは塾を立ち上げた時から守ろうと思った姿勢だ。
どう厳しいかと言うと、勉強をやらない生徒に対して「え?なんでやらないの?」という態度で接する。勉強は「やって当たり前でしょ」だ。やらないことに共感を示さない。耳も貸さない。そういう意味で、勉強をサボりたい生徒にとっては大変居心地の悪い塾のはずだ。だからそういう気のある生徒はすぐに辞めてしまう。
もちろんたまたま小テストの準備ができていないなどは、その理由を聞き、正当な理由は聞き入れる。しかし生徒が「このくらいならサボっても大丈夫そうだな」なんて思って仕掛けてくる駆け引きには一切乗らない。初手から全部潰す。おそらく他の塾ではなかなかできないと思う。
成績不振で転塾してきた生徒などは、他所でそれが通用しちゃったからここでも同じことをやろうとする場合が多い。しかし私は転塾してきた生徒はやがてここも転塾していくと考えているので、それが早いか遅いかだけならば塾のポリシーを取る。ここは託児所ではなく学習塾だ。学習姿勢の悪い方へ合わせることはしない。だからそれで定着できた子は確実に成績が上がっている。
「昨日の自分」は今日につながっているか

空腹を満たすためだけに惰性でしてしまった食事のことはすぐに忘れてしまうが、「今までで一番美味かったラーメン」と言われると意外とすんなり出てくる。印象深いものは記憶に残るからだ。
それと同じで惰性で過ごしてしまった日はあとになって思い出すことはできない。思い起こせるのはせいぜい後悔の念くらいだろう。そこで問いたい。「君は昨日何をやった?」
これで昨日のこと、特に勉強のことを事細かに思い出せるなら素晴らしいことだ。きっと昨日を精一杯生きたのだと思う。全く何をやったのか思い出せないのならば、それは昨日が「無かった」のと同じだ。受験生は特に、これからますます1日が重要になってくる。後になって思い出せない日にならないように過ごしてもらいたい。
最後まで一緒に

高校生が塾で使っている単語帳がある。生徒が高校1年生の時に渡したものだ。だからもう2年以上使っていることになるのかな。
今でもそれを使って授業で暗記テストをやっているのだけれど、もうボロボロ。ほんとにきったねぇの。側面はちょっと黒ずんでて、ページを開くとちょっとその黒ずみが紙面の縁にまで侵食してる。
でもそれを見るとね、
「ああ、これだけ繰り返し使ってくれてるんだなぁ」
って思えるのね。
問題が生まれた意味は、その問題が誰かに解かれたりしてその人の血肉になる為だと思ってる。その単語帳はほんと幸せ者だよね。
そのままだと自分の夢想した未来はどんどん遠ざかる

他の生徒よりも勉強量が少なくて、小テストも準備不足で不合格。
現状成績も学力も合格ラインに達していない。
これで「偏差値の高いあの高校に行きたい」というのは、
「ちょっと無理じゃない?」
と思うんだよなぁ。私は先々のことを見通す力は無いけれど、これは結構当たるんじゃないかなと思っている。
だって勝てる要素が無いじゃない。自分には運があるってか?受験ってそんなに甘いものじゃないよ。今までそれで泣いた先輩たちたくさん見て来たよ。自分は「特別だ」なんて思わないほうがいい。
自分事として捉えられるか

断言できるが、「他責思考」の子供は伸びない。
自分がやらないことを誰かのせい何かのせいにしているうちは、結果が好転することなんてありえない。成績が悪いのは教え方が悪いからだ。自習室は眠くなるから行きたくない。自分の外に原因を探す生徒はそもそも成績優秀者とは同じ土俵に立ってすらいない。
成績の良い生徒は勉強を「自分のもの」と捉えて取り組んでいる。自分が主人公のストーリーを歩んでいる。困難にぶつかったら自分で乗り越えようとする。だから人から応援される。その結果他責思考の生徒よりも支持を集め、手厚いサポートを受けるようになる。誰でも一生懸命頑張っている人を応援したいのは当然だ。周りの人を自分のファンにできる人が成長を加速させていく。
第4回北辰テストに向けて

明日は中3の第4回北辰テストだ。弊塾の中3生も全員申し込んでいる。
これは夏休み後最初の模試となるので、生徒の夏休みの学習の成果を見るものであり、また受験校を絞り込んでいくための非常に重要な資料だと考える。
これまでの受験生たちが証明してくれているので断言できるが、夏にしっかり勉強ができた生徒は必ず成績が上がっている。夏期講習でそれだけのものを提供したし、私がやれることはやり切った。あとは生徒が明日力を出してくるだけだ。
ここで偏差値が5以上伸びる子は、まず本来そのままで行ったら受験するであろう高校よりもレベルの高い高校を受験することになる。そうすると囲まれる友人や先生も変わる。そのまま頑張り続ければその後の進路も変わる。つまり人生が変わる。そういう子が出てくることを期待している。
生徒から素敵なお土産をもらった話


生徒から夏休みのお土産をいただいた。ありがとうございます。
生徒のみんなには悪いが、たこせんいかせんは私の個人バッグに入れさせていただいた。いやあすまんな。
その他にも、生徒が訪れた場所のパンフレットをお土産として持って来てくれた。この心遣いは嬉しい。
この年になると物を手に入れること以上に、経験を得るのが嬉しく感じるようになってくる。たまに生徒にも休み期間の話などは聞くが、業務の中だとなかなか時間をかけてじっくりというわけにもいかない。なのでこうした形に残る経験のおすそ分けはありがたい。生徒からの土産話は、生徒がまたここに戻ってきてくれた嬉しさとともに噛みしめられる。だからとても美味い。
テストへの姿勢

テスト。
定期テスト、入試、小テスト、単元テスト。なんであれ、「テスト」と名の付くものには全力であたるべきだ。「そこそこ」な準備で臨むなんてありえない。
テストとは自分への評価だ。自分が「そこそこ」であるという見られ方に満足する人なんてきっといない。他人と比べた優劣はどうしてもついてしまうが、自分の全力でない結果を自分の実力とされてしまうことにもっと恐怖を感じよう。
昔いたある生徒は、テストの直前になると手が震えてしまっていた。学年1桁、塾でトップの成績だったが、
「テスト直前は緊張する。怖い」
とよく言っていた。
自分の最高が出せない恐怖。そんなものと戦っていたのだと思う。この姿勢がその子をトップへと押し上げた。
小テストで不合格になってもヘラヘラしている君!「まあ別に本気じゃなかったしぃ」という言い訳のための手抜きなんて今すぐやめて本気になろうぜ。
そこから何が見える?

もくせい塾は「自習ありき」の仕組みになっている。
毎回の授業で小テストを行うので、その準備の為に塾に来ることになる。私は、自宅で勉強するのは難しいという立場だ。自分自身もそうだったし、長年生徒を見ていて自宅学習が上手くいっている生徒はほんの一握りだったからだ。ただし、塾に通わずに自宅学習が上手くいっている生徒もいるだろうがそれは私の関知できないところである。私も含め多くの生徒にとって、誘惑が多く甘えが許される自宅学習はハードルの高い作業だ。
だから塾に来させる。そうすることで勉強ができる。勉強しかない環境に身を置くので成績も上がる。まあ当然生徒は嫌がる。それは面倒な作業だからだ。何かしら理由をつけてサボろうとする生徒もいる。しかしそういう生徒に差し伸べられる手はここにはない。テストの準備をしないと授業は進まないし、私がこのルールを曲げることはないからだ。ここで合わせられない生徒は退塾してしまうこともあるがやむを得ないと思っている。入塾時にこのルールは説明をして納得した上で入ってもらっているし、ウチの売りはこの仕組みで成績を上げることにある。生徒に甘やかしの手を差し伸べても結局長続きしないことも散々経験してきた。
新しく入った生徒が初めの2週間自習に来ず授業が進まなかったが、ここに来てよく自習にくるようになった。ルールに馴染み、自分で歩くことをはじめられたようだ。
きっと彼の眼前には無限に広がる学問の世界が広がり、そこを自分の足で歩ける自由を感じていることだろう。第一の関門を突破することに成功したこの子は、すでに今までとは違う景色を見ている。
台風10号

台風10号が週末にかけて近づいてきている。今週後半の天気は荒れるかも知れない。通塾時は十分に注意してください。
台風と言えば、夏期講習の理科では日本の天気に関しての暗記テストを行った。梅雨を加えた四季の天気をまとめたものを暗唱してもらうだけなのだが、なんと今年はこれに合格できた生徒がたったの2名だけだった。
正直「情けないなぁ」と思う。去年まではほぼ全員が合格していたものだ。テストをしてみると、途中までは覚えてきたのだろうなという感じに進むが、ある程度までくるとピタッと止まってしまう。「ここまでやったからいいよね」という自分に対するエクスキューズが見て取れる。中には「無理だから諦めた」と言っている生徒までいた。まったく嘆息ものである。入試は「ここまで頑張ったからいいよね」は通用しない制度だ。今後の奮起に期待したい。
さて、合格した2人だが、どちらも女の子だった。こういうものに性差は無いと信じたいが、私の経験上、土壇場で根性を見せるのは女の子のほうが多い。もしかしたら子育てにおいて、男の子と女の子への親御さんの接し方に何かヒントがあるのかも知れないと思っている。
夏期講習の振り返り➀

夏期講習も終わったことだし、気付きと感想を書いておく。
今回の夏期講習では大きな変更点がひとつあった。例年は午前9時から行っていたが、今年は部活動の兼ね合いでそれだと参加できない生徒も多く12時半からへ時間帯を変更した。
それにより、生徒の体力的には楽になっていたように感じる。1日の大きな休憩時間が夕食時のみとなってしまったが、午前中に授業が無いので特に問題は無かった。
そのいっぽうでテスト道場が毎日開催できず、テストの頻度が減ってしまったことが悔やまれる。分量は減らさないようにしていたが、直前に準備しようとする生徒は間に合っておらず不合格を繰り返した。成績を上げるにはテストは「毎回」行うべきだと感じた。
しかし、それを自分で補う生徒も出て来たことを補足しておく。講習が終わって私の時間がある時に、不合格だったテストの再テストを申し込む生徒が何名かおりそれに付き合った。再テストでは合格するまで繰り返していたので、かなりの学習効果があったと思う。私もやる気のある生徒の姿を見ることができて励みになった。
新学期スタート

今日は始業式。夏休みも終わって通常運転再開だ。
私も夏期講習が終わってホッと一息ついたところだ。
塾講師にとって夏期講習はひとつの大きな山場になる。
受験生にとっての大切な時期であり、その一旦を担うものだから絶対に中途半端なものは出せない。真剣勝負のつもりで毎回の授業に臨んだ。今年は途中で少し喉がかすれたが、体調も万全のまま無事に乗り切れた。夏期講習についての感想はまた記していきたい。
講習の最終日は、ちょうど「南越谷阿波踊り」の日でもあった。
私は夏を頑張った生徒たちを労う意味で、その日の課題は「なし」にした。行きたければ遊びに行ってもいいよ、と。受験生でも少しくらいは夏に彩りがあってもいいだろう。
しかし授業後、何人かの生徒から「課題をください」との言葉を頂戴した。夏前の様子を見てかなり不安があったのだが、これは私の想像を超えてきた出来事だった。
受験の合格発表で大きな祭を開催しような。
先週お問合せいただいた方
先週弊塾へお問合せ下さってまだ返信が無くて、
これを読まれている方がいらっしゃいましたら、
お手数ですがもう一度ご連絡下さい。
いただいたメールを返信してもメールが戻ってきてしまっております。
つきましては、別の連絡手段をお伝え下さると幸いです。
よろしくお願いいたします。
【塾生のみなさんへ】お土産をいただきました!

生徒からお土産をいただきました。ありがとうございます!
ポストの横にあるので、ほしい人はどうぞ~。
夏期講習25日目

夏期講習25日目。最終日!
1時間目は英語を行なった。長文読解で精読を行った。適宜足りない知識を補いながらやっていった。入試の英語長文読解に必要な知識をどんどん紹介しながら説明したので、頑張って覚えていってもらいたい。2時間目は数学。1行問題の演習・解説と北辰テストへ向けた問題演習を行った。1行問題の出来はまずまずだったので、今後もミスをしないことを目指して数学の勉強をしていってほしい。3時間目は理科。問題演習で、植物と動物のからだのつくりと働き、化学変化の部分を扱った。知識問題は記述も含め、かなりできるようになってきたと思う。4時間目は社会。歴史の全範囲を終らせ、地理の総合問題演習と解説も行った。
夏期講習24日目

夏期講習24日目。
夏期講習も残すところあと2日。
1時間目は数学を行った。1行問題をひたすら解いて解説。埼玉県立高校入試や北辰テストの大問1の対策になる。基礎的な問題が多かったので、ここで間違えることなく正解し、得点を積み上げていってほしい。2時間目は理科。問題演習を解説を行っている。地震の問題と、地層と堆積岩の問題を行った。ボーリング資料の問題は正答率が低めになりがちなので解解き方を説明した。3時間目は社会を行った。高度経済成長期から現代、そして今後の課題まで。地域紛争の話もできるだけ詳しく話した。4時間目は英語を行なった。文法問題の演習・解説を英語長文の精読を行った。知識を増やしながら英語を読んでいった。
夏期講習23日目

夏期講習23日目。
本日1時間目は理科から行った。演習問題で知識の確認。凸レンズの問題を解説した。序盤の授業で行った凸レンズの作図を思い出しながら問題を解いてもらった。そして音、力の問題、火成岩と地震の問題演習まで行った。知識はだいぶ入ってきたけれど、力の計算問題などはまだできない子もいるので、これから練習していってもらいたい。2時間目は社会。戦後日本の民主化から高度経済成長のあたりまで説明した。3時間目は国語を行った。表現分野で日本語の使い方を勉強し、その後作文指導へ。入試で作文にかけられる時間はほとんど取れないので、その話も伝えて実際に制限時間を設けて1本書いてもらった。4時間目は英語を行なった。分詞の形容詞的用法を復習した。その後、総合演習に入った。
【塾生のみなさんへ】お土産をいただきました!

生徒からお土産をいただきました!ありがとうございます。
ポスト横にあるので、ほしい人はどうぞ。
夏期講習22日目

夏期講習22日目。
1時間目は社会を行った。世界恐慌から第2次世界大戦まで。戦時下の世界と日本の情勢を伝えた。2時間目は国語。前回に続き国文法を行った。短文を文節・単語に分けて品詞分類する練習を行った。3時間目は英語を行なった。現在完了形の後半、継続用法と現在完了進行形について説明した。4時間目は数学。引き続き総合問題を進めている。そろそろ第4回北辰テストを意識した演習を始めているので、そこで夏期講習の成果を実感してもらいたい。
夏期講習21日目

夏期講習21日目。
1時間目は国語を行った。文法の学習に入った。品詞分類ツリーを覚えて、用言の活用、文節・単語分けから品詞分類の練習を行った。文法への苦手意識は基礎事項の暗記不足からくるものだ。この時期になって文法学習の全容が見えてくると覚えるべき事柄も見えてくるので頑張ってもらいたい。2時間目は英語。現在完了に入った。完了用法・経験用法の文について復習した。みんな文法の形は理解できているので、副詞などから用法の区別がしっかりとつくようにしてほしい。3時間目は数学。総合問題を解き進めている。方程式の文章問題、図形問題などを演習して解説し、その中で受験に有用な定理も教えた。4時間目は社会。歴史の第1次世界大戦の終わりまで進んだ。
勉強に必要なもの。逃げない意志

今日の夏期講習ではひとつ話をした。夏季休業中の課題の出来が気になったからね。
頭の良さは遺伝するという研究結果があるけれど、勉強に関して、私はそうは思っていないという話。
もし勉強に才能があるとしたら、目の前のことを「ちゃんとやる」ことができるのが才能だと思っている。どれだけ頭の良い遺伝子を受け継いでいようが、目の前のことから逃げているうちはその才能が花開くことはない。
逆に言えば、どんなに才能が無くても目の前のものにきちんと取り組んで、1ミリでも成長していければそれはやがて大きな蓄積になる。たかだか高校受験程度の学問に才能の差なんてほとんど影響しない。やるか、やらないか、つまりそれだけだ。
本当は久々の授業だったし、アイスブレイクも必要かと思って私の休暇中の珍道中を話して聞かせようとしたのだけれど、生徒はさっそく興味がなさそうだったのでこちらは早々に切り上げた(残念)。その後テストの出来を見て上の話をすることになった。こっちはみんな神妙な顔をして聞いてくれた。
【塾生のみなさんへ】差し入れをいただきました!

夏季休業中のお土産をいただきました!ありがとうございます~。
ポストの横にあるので、ほしい人はどうぞ!
夏期講習20日目

夏季休業が明けた。夏期講習20日目。今日は、休み前に告知しておいた通り休業期間中に出した課題のテストを行っていった。
はじめに漢字テストを行った。1回目の結果は半数が不合格となり再テストを行った。出来もかなり悪く、ギリギリ不合格どころか明らかに休み期間に勉強していないのが分かる有様だった。もうちょっと頑張ってきてほしい。
その後社会の用語集、理科の暗記シートのチェックテストを行った。社会のほうはまずまず、理科はまだ半分も合格できてないかな。理科のテストの途中で時間が来てしまったので、残りと他の科目のテストはテスト道場で引き続き行う。
夏季休業

本日からもくせい塾は夏季休業に入った。
今日はやることがあって教室に来ていたが、明日からお休みをいただく。
中3受験生には休み明けに行うテストの為の勉強の指示を出しておいた。もちろん学校の課題もね。あとは受験生とは言え、適度な休養も必要なのでバランスよく過ごしてもらいたい。
他の学年の子たちも帰省する子や部活動に勤しんでいる子もいるようだ。よい夏を過ごしてもらいたい。休みが明けたらまた元気な顔を見せにおいで。
それではご迷惑をおかけしますが、英気を十分に養ってきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
夏期講習19日目
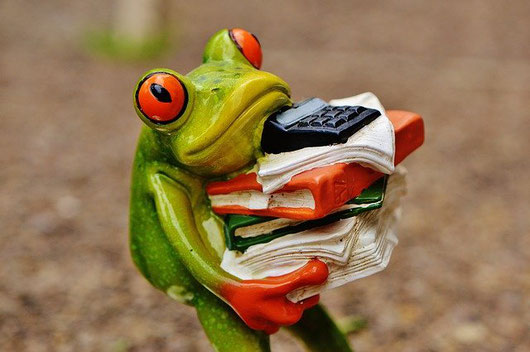
夏期講習19日目。
今日が夏季休業前最後の夏期講習だった。
1時間目は数学。1,2年生の範囲の復習2周目を行っている。苦手範囲になりがちなのは空間図形や関数などの、覚えるべき公式があるところだ。公式は授業のたびに全員で公式集を唱えているのだが、実際に使えるようにするには問題演習を積むしかない。今日も多くの問題を解いたので、すこしずつ身になっているという実感を感じられていると思う。2時間目は理科。1,2年の総復習2周目を進めている。物質の密度、溶解度の問題では計算が出てきたので解説も行った。また混合物の分離の実験考察問題はよく出てくるので確実に正解しておきたい。3時間目は社会。明治維新から日清・日露戦争そしてその後まで説明した。4時間目は国語を行った。漢文の読解問題と漢詩の知識を説明し、文法の学習に入った。
夏期講習18日目

夏期講習18日目。
1時間目は理科を行った。仕事とエネルギー、力学的エネルギーの保存について説明し、その後学習内容の2周目に突入。中1の化学分野の演習に入った。2時間目は社会。江戸時代の滅亡から明治維新までの解説を行った。3時間目は数学。平方根の範囲を終らせ、こちらも学習内容の2周目に入った。標準問題演習で内容の復習を行っていく。立体の表面積が出せない子は、展開図を必ず自分で書くようにしてほしい。4時間目は英語。文型の復習を少し行い、受動態の説明へ。能動態との書き換え、第4、第5文型の受動態の説明などを行った。ここまで夏期講習を受けていた生徒たちならば、受動態がどういったものがよく分かってくれたと思う。
夏期講習17日目
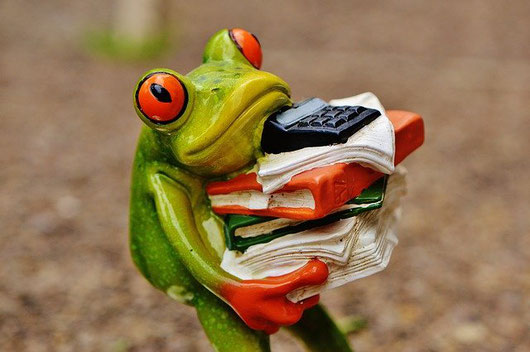
夏期講習17日目。
今日の1時間目は社会から行った。歴史で、開国から倒幕の話まで。このあたりは幕府だけでなく、外国や藩の動きも理解しなくてはならないので流れをしっかりつかんでほしい。2時間目は国語。古文の読解練習と漢文の読み方について行った。3時間目は英語を行なった。文型について説明した。第4文型と第3文型の書き換え、第5文型に使われる動詞などを紹介していった。文の成分の指摘はだいぶできるようになってきた。4時間目は数学。因数分解の範囲を終えて、平方根の計算に入った。
夏期講習16日目

夏期講習16日目。
1時間目は社会を行なった。江戸時代の説明を進めた。改革の内容と文化について説明が終わった。2時間目は英語。接続詞を終らせ、文型の説明に入った。文型はあまり学校でまとめて説明を受けていないかも知れないけれど、英語の長文を読むときにはとても大切な考え方になるのでしっかり理解できるように頑張ってほしい。3時間目は数学を行った。いよいよ3年生の範囲に入った。式の展開と因数分解の途中まで一気に行った。この範囲は最近学んだので特に問題なく進むことができた。4時間目は理科。力のはたらきについて、つりあい・作用反作用・慣性の法則などについて説明した。
夏期講習15日目

夏期講習15日目。
1時間目は英語を行なった。前回説明した原形不定詞の構文の復習を兼ねて問題演習から。通常授業でもまだ触れていない子もいるので、問題を解きながら身に付けていってもらいたい。その後接続詞の説明に入った。等位接続詞、従属接続詞の基本を説明した。2時間目は国語。古文の読解練習を行った。今回からは私の解説ではなく、生徒に文法事項の指摘と訳を任せてみた。こうして自分でできるようになっていくことが大切だ。3時間目は理科を行った。日本のまわりの天気の変化のところを終らせて、力と運動の範囲に入った。もうすぐ全範囲を終えられそうだ。4時間目は社会。安土桃山時代から江戸時代の初期までの解説と問題演習を行った。
夏期講習14日目

夏期講習14日目。今日から夏期講習は後半戦。また、今週1週間やったら夏季休業をはさむことになる。
1時間目は数学。場合の数と確率を行った。樹系図などまだ書きだすことに慣れていない子もいたので基本問題の解説を行った。正しく書き出せば計算間違いを起こすようなところではないので、入試では確実に得点につなげたい。2時間目は理科を行った。天気分野について説明した。気象の要素から湿度の計算、日本の四季の天気についても話をした。3時間目は社会。鎌倉時代・室町時代まで説明を行った。4時間目は国語。古文の読解練習を引き続き行った。
水道が直った

教室の水道関係が解決した。
昨日調査してもらった結果、ポンプの安全装置による「高温による緊急停止」だったそうだ。なのですぐに直った。今日から普通に水が使える。良かった。
それにしても高温て。今の気温って本当に危険な水準だということが分かるね。教室の中は涼しくしているけれど、水分補給等しっかり行ってほしい。
まだ水が出ない

教室の流し・トイレの水が出ない問題だが、どうやら建物自体のトラブルのようだ。昨日不動産屋さんに確認してもらった。
どうやら水を3階まで上げるポンプ室に原因があるようだ...ということで明日管理会社のほうできちんと調査して、今後その修理をしていくことになるそうだ。まだ時間を要する、困った。お手洗いは1階のものを借りられるようにできたので緊急事態は逃れたけれど、フロアの水が出ないのは単純にツライ。早く直ることを願う。
夏期講習13日目

夏期講習13日目。
夏期講習も今日で折り返しだ。
1時間目は理科。電気と磁界の説明から。右ねじ・フレミングの法則、電磁誘導からモーターの構造まで説明し、天気分野に入った。2時間目は社会を行った。奈良時代の終わりから平安時代、鎌倉時代まで入った。3時間目は数学。資料の整理、度数分布表とヒストグラム、箱ひげ図の書き方を説明した。4時間目は英語。不定詞の構文と原形不定詞の文について説明した。
それにしてもテスト道場の合格率が悪すぎる。漢字テストを毎回不合格している生徒がいるので再テストをしてそれで終わってしまうので、もう少し奮起を促したいところ。
夏期講習12日目

夏期講習12日目。
1時間目は社会から行った。歴史の縄文時代~奈良時代の範囲を説明していった。まだテキストの用語を軽くさらっている段階なのだが、ここで流れをつかんでいってほしい。2時間目は国語。古文の読解に入った。主語を確認しながら教えたテクニックを使って一緒に読んでいった。3時間目は英語を行なった。不定詞・動名詞の基本を説明した。不定詞は、文構造をしっかり理解していなくてはただの「to+動詞の原形」止まりだ。それを抜け出して更なる英語の理解を深めていってほしい。4時間目は数学。図形の角度の問題の続きを行い、その後三角形の合同、二等辺三角形と平行四辺形の性質の解説と演習を行った。